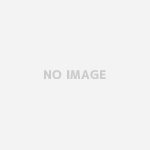スタジオジブリの製作現場を描いたドキュメンタリ映画『夢と狂気の王国』を観てきました。
スタジオジブリの製作現場を描いたドキュメンタリ映画『夢と狂気の王国』を観てきました。
ジブリを題材にしたドキュメンタリというと、これまでにも沢山あって、一つの作品が出来るまでの過程を追ったメイキングものだったんですけども、今回の映画はそうではなくて、一本の映画として観ることができる作品でした。
かといって、メイキング場面がないわけでもないのだけれど、焦点はそこではないんです。
『夢と狂気の王国』というタイトルにもあるとおり、ひとつの王国であるスタジオジブリを描き、王様を含めてそこで働くスタッフや、映画作りに関わる人たちを描いた、ひとつの国の物語という感じでしょうか。
さて、その王様は誰なのかということは、はっきりとは描かれていません。絶対的な力を発揮する宮崎駿監督のようでもあるし、それを支える鈴木敏夫プロデューサーのようでもある。はたまた、その二人の上に君臨するかのような存在感を放っている、高畑勲監督でしょうか。これは、観る人によって受け取り方は、違ってきそうです。
例えば、この三人のうち、誰か一人でも出会うことがなかったら、スタジオジブリは存在していないはずです。だから、三人の王様とも取れますね。

ただ、宮崎駿監督が、この映画の主人公であることは間違いありません。取材の期間は、一年前から、つい先日まで行なわれていたようです。『風立ちぬ』を作る宮崎監督と、それを支えるスタッフたちが、どのようにジブリでの生活を過ごしているか映します。この宮崎監督の周りの人間模様を描いたところが、これまでのジブリを扱ったドキュメンタリとは決定的な違いでしょうか。宮崎監督の功罪がちゃんと描かれています。

この映画を観て、退屈に思う人もいるかもしれません。映画のメイキングを期待していたり、創作にかける狂気の部分を期待していると物足りなくもなりそうです。実際、ぼくもこの作品は「夢」の部分が強くて「狂気」があまりないと感じました。
夢のなかの空間で織り成す人間ドラマに終始しているかもしれません。
ただ少し、この国には狂気も孕んでいるんだぞ、という、ぞわぞわしたものは滲み出ています。それは、宮崎駿監督の内にあるものという印象で。宮崎吾朗監督と、川上量生さんが対峙しているシーンは、狂気というよりも、生きる苦しみのようなものを強く感じた。

この映画で心に残ったことは、夢ような空間のスタジオジブリと、宮崎駿監督の面白さ。ここのところ盛んに語られている、宮崎駿監督は矛盾を抱えた人間であるということ。きっと、矛盾のない人間なんていないでしょう。
しかし、宮崎監督は、ひときわ大きな矛盾を抱えています。おそらく、小さな矛盾を乗り越えながら、大きな矛盾に立ち向かってきた人なんじゃないのかな。
ある種、体育会系のような厳しい一面を持ちながら、人の心に寄り添うようなとても優しい気持ちを持っているのは、陰と陽の両方あるからなんだと思います。
『Switch 12月号』で交わされた、糸井重里さんと川上量生さんの対談にもあるように、「影のある人じゃないと人に優しくなれない」という言葉のとおりで。宮崎監督は、とても大きな影を持ちながら、これまでサバイブしてきたんじゃないのかな。それゆえに、他人を破壊してしまうような強さと、大きな優しさがあるのだと思う。

この映画の中盤あたりだったかな。宮崎監督が子供の頃の出来事が語られていた。戦後間もないころ、ある子供に対して、父親が取った行動が、肯定的な結果となって返ってきたときの話には泣けてきた。
「そのときの子供は、ずいぶん世の中の見方が変わったでしょうね」という言葉だったかな。ほんとうに宮崎監督は、奥深い優しさを持っているなと思った。
ほんの些細なことだったのだけれども、ある好意的なことを子供時代に受けたことで、その人間に大きな影響を及ぼすことはあると思う。
ぼく自身が、子供のころから宮崎監督の作品に育てられたこともあって、彼の一貫している子供への愛情が伝わって泣けてきた。人間という存在を憎む一方で、人への愛情がひときわ強い。なんて人間くさくて、愛くるしい爺さんなんだろう。

エンディング間際、砂田監督を呼び寄せて、街を見下ろして語るシーンは、遺言のようだった。
「こうやって世界を見ると面白いでしょ」ということを言っていたけど、それは映画のワンシーンとシンクロさせる演出と相まって、これまで宮崎監督が描いてきた「人生は生きるに値するんだ」というような、「生きろ」というような、最後のメッセージのように受け取れた。
宮崎駿という被写体を通して、宮崎駿作品を観たようだった。