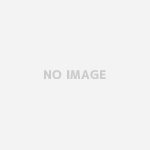僕が参加している、ボーイスカウトはなんなのか。について、ちょっと書いてみる。
軍隊のような制服に、首にスカーフをまいた少年たちを見れば、ボーイスカウトだと分かる人は多いかもしれない。
しかし、知名度は抜群に高いのに、どんな団体なのかは、あまり知られていなかったりもする。

始まりは、イギリスの軍人ベーデン・パウエルが、青少年の心身を健全に育成するために創始したと伝えられている。この話はたぶん有名。
では、このベーデン・パウエルが、ボーイスカウトの教育システムをどうやって創りだしたのか。
これは、あまり知られていないけれど、鹿児島の郷中教育を参考にしたといわれている。
これには諸説あるようだけれど、乃木希典大将の日記に記された話を、正しいものとして話を進める。
乃木大将がボーイスカウトの訓練を視察した際に、パウエル卿にボーイスカウトの制度をどのようにして創られたのかと尋ねた。パウエル卿は「あなたのお国の薩摩における“郷中教育”の制度を研究し、そのよい点を採り入れ組織しました」と答えたという。
郷中教育
鹿児島には、『郷中教育』という薩摩藩の伝統的な縦割り教育がありました(『ごじゅうきょういく』、または『ごうじゅうきょういく』とも呼ばれます)。郷中とは、町内の区画や集落単位の自治会組織のことで、今でいう町内会と考えればいいでしょう。当時、鹿児島の城下には数十戸を単位として、およそ30の郷中があったと言われます。
郷中は、青少年を「稚児(ちご)」と「二才(にせ)」に分けて、勉学・武芸・山坂達者(やまさかたっしゃ、今でいう体育・スポーツ)を通じて、先輩が後輩を指導することによって強い武士をつくろうとする組織でした。
稚児は年齢によってさらに、6・7歳~10歳の小稚児(こちご)と11歳~14・15歳の長稚児(おせちご)に分けられ、稚児のリーダーとして稚児頭(ちごがしら)がいました。また、二才(15・16歳~24・25歳)のリーダーとして二才頭(にせがしら)がいて、二才と稚児の面倒をみていました。
年長者は年少者を指導すること、年少者は年長者を尊敬すること、負けるな、うそをつくな、弱い者をいじめるなということなどを、人として生きていくために最も必要なこととして教えました。この郷中教育は、文禄・慶長の役(1592~98年)のとき、残された子どもたちの風紀が乱れないように始められたと言われます。

では、なぜパウエル卿が郷中教育を知ることになったのか?
これには、二つの説があるようだ。
1868年に起きた、薩英戦争を切欠として、イギリスの日本に対する政策が変わり、薩摩藩とイギリスの親近関係は深まったという説。
もうひとつは、日露戦争。
日本が勝てるわけがない。世界の大半にそう思われていた戦争だったけれど、日本の連合艦隊が、ロシアのバルチック艦隊を一方的に打ちのめし、日本が勝利してしまった。これで世界が驚いた。
このとき、連合艦隊の指揮をしていたのが東郷平八郎。
そして、満州軍総司令官が大山巌。あの西郷隆盛の親戚としても有名な人。
陸海ともに勝利を収めたこの優秀な指揮官が、少年時代を薩摩の郷中教育で育ったという事実。
これを知ったパウエル卿が、薩摩の郷中教育に関心を持って、ボーイスカウトの教育法を創りだしたともいわれている。
どちらが正しいのかは分からないけれど、ボーイスカウトの根っこに、薩摩の郷中教育があるのは有力らしい。

こうやって、外部からの血によって、日本の遺伝子が継承されていくのは、少し嬉しくて、少し寂しくも感じる。どうせなら日本で発展を、と思えなくもないけれど、そもそも継承される先には、その必要性があったということ。何かしら危機的な状況があって、このままではいけない、と追い込まれた末に新しいシステムが生まれることになる。
そして、イギリスで発展したボーイスカウトは、20世紀初頭に世界中へと拡がった。
日本に入ってきたのは、明治の終わり頃。当初は「少年団」という名前で発足している。ボーイスカウト日本連盟と改名されたのは、昭和23年のこと。それ以後、凄まじい普及率でボーイスカウトが拡がって、世間に認知されていくことになる。

しかし、ここ最近は急激な時代の変化で、ボーイスカウトの人気にも陰りがみえはじめてきた。いくつもの団が解散へと追いやられ、地区の合併なども行われている。外国ではどうか分からないけれど、日本においてボーイスカウトが衰退してきているのは間違いない。僕が参加している団も人事ではない。
ボーイスカウト日本連盟の登録者数は、昭和58年の33万人をピークに年々減少している。現在では、当時の半分以下にまで落ちこんでしまった。つまり、数字のうえでは30年後にボーイスカウトは消滅していることになる。
こうなってくると気になるのが、今度はボーイスカウトの遺伝子がどう継承されていくのかということ。
ボーイスカウト内で直系の継承をして、新しいボーイスカウトへと生まれ変わるのか。
それとも、パウエル卿が行ったように、外部からの血によってボーイスカウトの良い部分を汲みとって、まったく新しいものに展開されるのだろうか。
僕としては、新しいボーイスカウトが見てみたい。